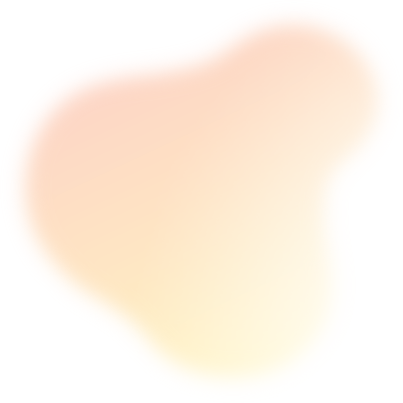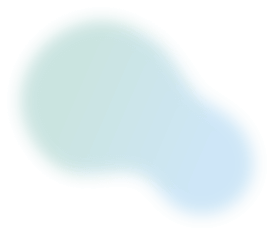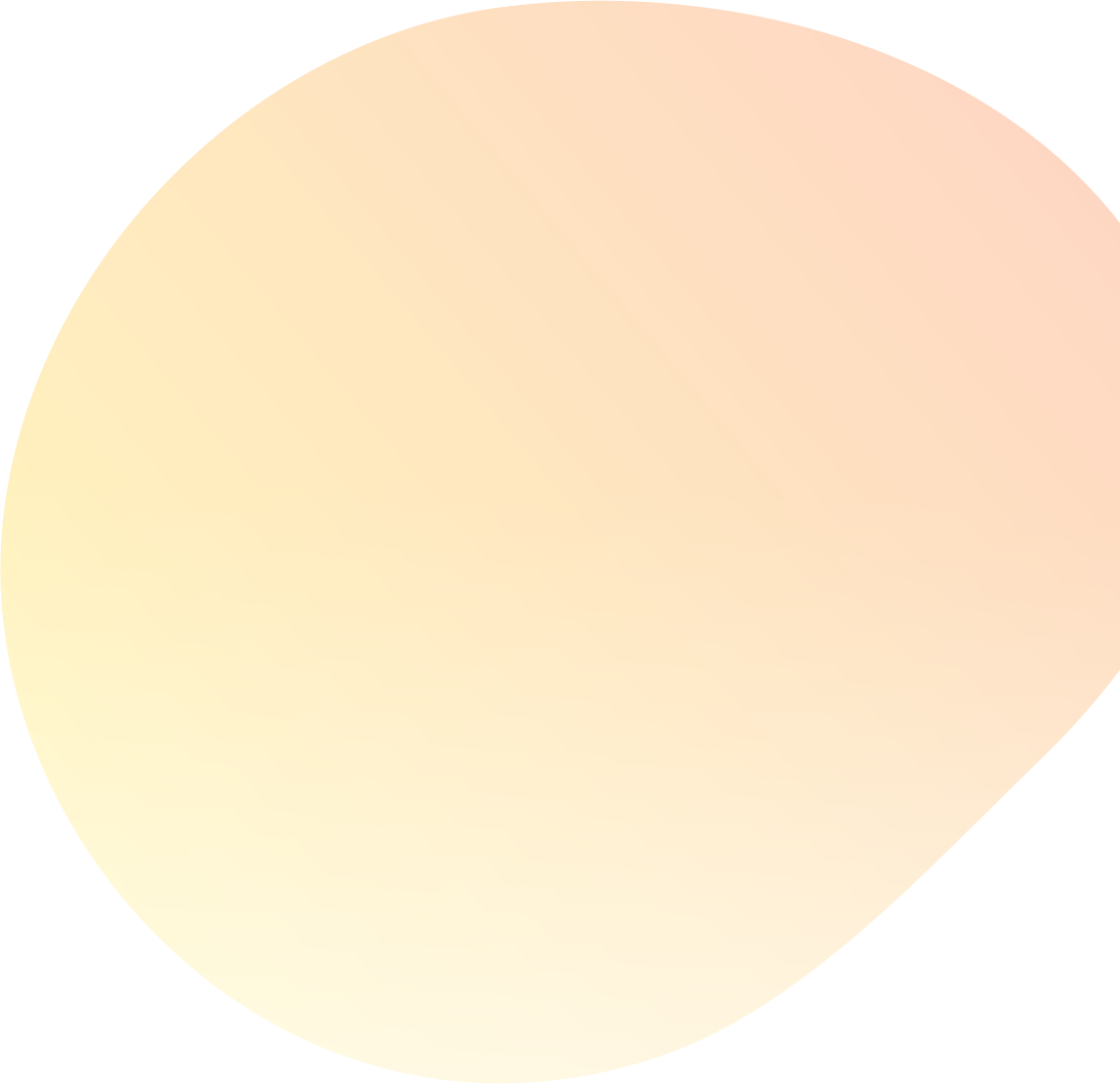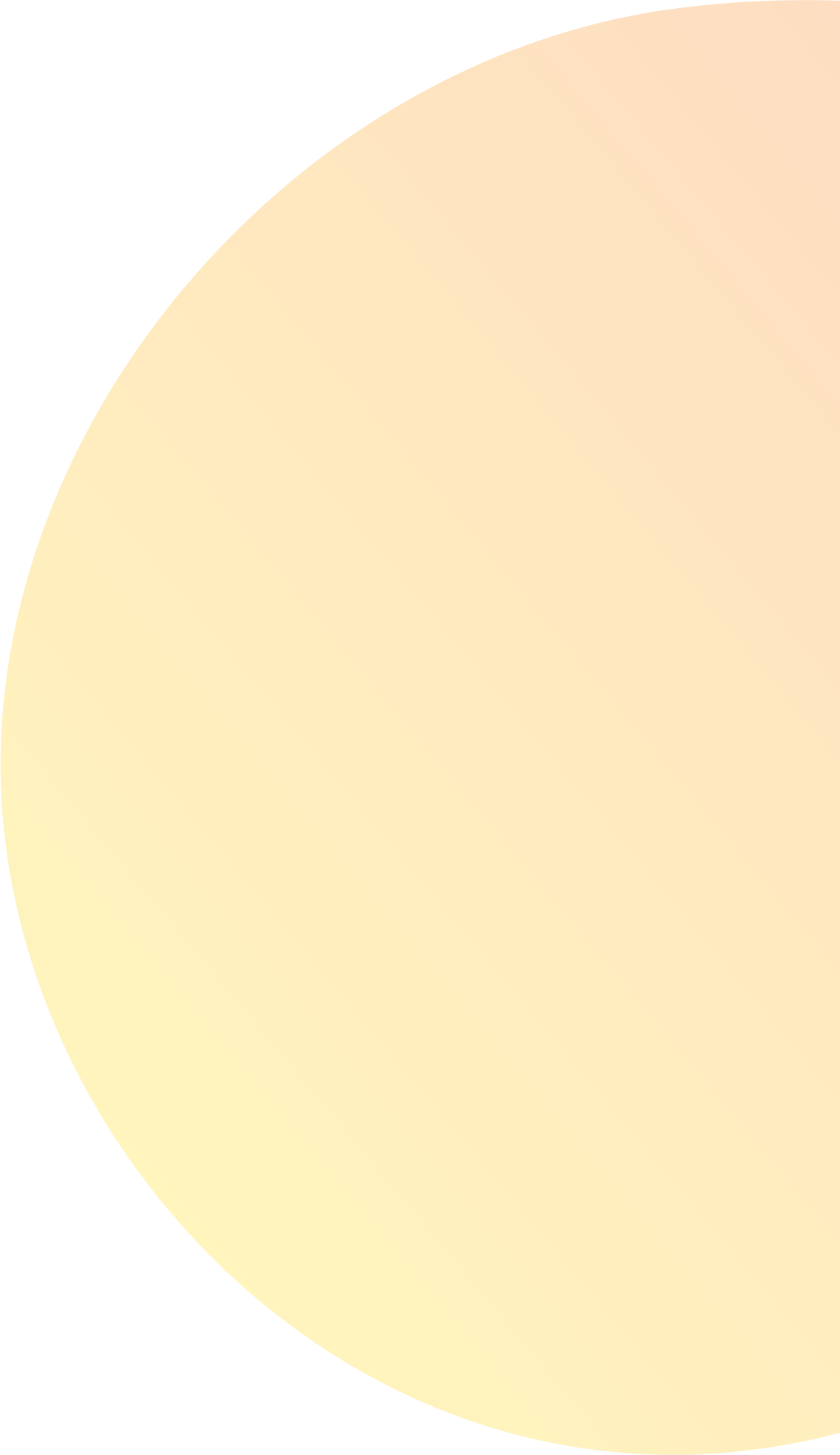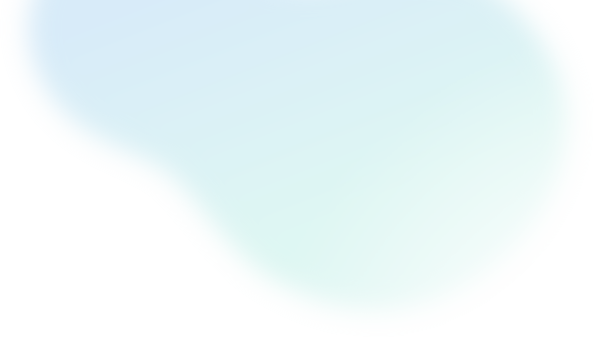“Social Well-being”とは何か?





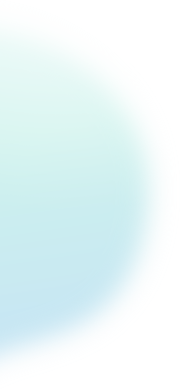




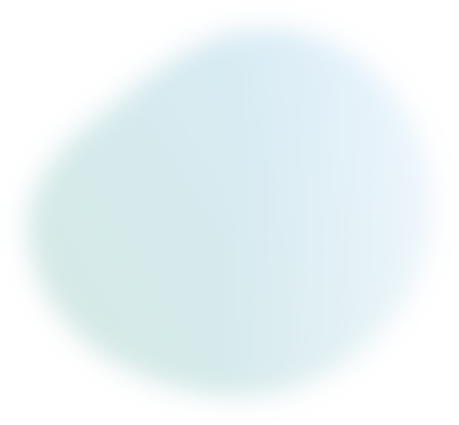

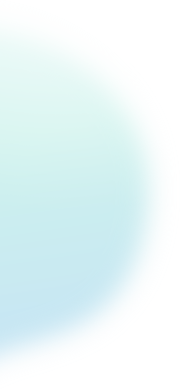




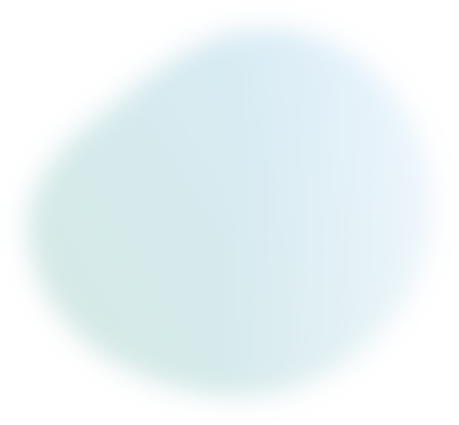
なぜ“Social Well-being”?

まず、私たちがSocial Well-beingを重視するきっかけとなった出来事の1つとして、2020年の新型コロナウイルスの流行による社会的距離(ソーシャルディスタンス)政策があります。この政策によって、多くの会社員は、会社に集まることができなくなり、自宅でのリモートワークをすることを余儀なくされました。
そして、リモートワークによる新しい働き方は、新型コロナウイルスの流行が抑えられつつある現在、一部の企業・職種において継続しています。
国土交通省の令和4年度の調査によると、雇用型就業者の26.1%がリモートワークを実施しており、雇用型リモートワーカーの86.9%がリモートワークの継続意向を示しています (参考文献1)。
また、NTTグループは、日本全国どこからでもリモートワークを可能とする制度を定め、リモートワークを基本とする新しい働き方を推進しています (参考文献2)。
これまでの研究では、リモートワークは仕事に対する満足度や仕事のストレスの低下などの利点がある一方で、オフィスでの対面コミュニケーションの機会を失うため、社会的な孤立を生み、同僚や上司との人間関係の質、イノベーションに悪影響を及ぼすことが懸念されています (参考文献3)。
つまり、物理的な距離が離れているリモートワーク環境において、いかにして人と人とのつながりを維持し、Well-beingな職場環境を構築するかが課題になってきます。
このような背景から、私たちの研究プロジェクトでは、人と人とのつながりに基づくWell-beingを重視し、Social Well-beingを念頭に置いた情報通信技術をデザインする研究開発に取り組んでいます。
Social Well-beingの定義
Well-beingという用語自体は、1946年に採択された世界保健機関(WHO)憲章 (参考文献4)における健康の定義(以下)に含められたことにより、広く一般的になりました。
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”(日本語訳:「健康とは、肉体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に病気や虚弱のない状態ではない。」)
その後、様々な研究者がSocial Well-beingという用語を定義しています(表1)。私が調べた範囲では、統一的な定義は見当たりませんでしたが、これらの定義に共通している点として、「自分が属する集団・社会との関係性の質」に焦点が当てられています。
| Social Well-beingの定義 | 参照 | |
|---|---|---|
| 1 |
“that dimension of an individual's well-being that concerns how he gets along with other people, how other people react to him, and how he interacts with social institutions and societal mores” (日本語訳:「個人のWell-beingの次元であり、他の人々とどのようにうまく付き合っていくか、他の人々が自分にどのように反応するか、社会制度や社会的モラルとどのように関わり合うかに関係する」) |
Russell (参考文献5) |
| 2 |
“an individual's self-report of the quality of his or her relationship with other people, the neighborhood, and the community” (日本語訳:「他の人々、近隣、コミュニティとの関係の質に関する個人の自己報告」) |
Keyesら (参考文献6) |
| 3 |
“overall social quality of life, in terms of a person’s link to other people and society on the whole” (日本語訳:「他の人々や社会全体とのつながりという意味での社会的な生活の質全般」) |
Lintonら (参考文献7) |
| 4 |
“well-being at the group or community level, i.e. how the individual responds to experiences of the social environment which can affect their health” (日本語訳:「グループやコミュニティレベルのウェルビーイング、つまり、個人が健康に影響を与え得る社会環境の経験にどのように反応するかということ」) |
Baldwinら (参考文献8) |
| 5 | 複数の個人の自律を担保しつつも、そのつながりから集団のよい状態が実現されるWell-being | NTT社会情報研究所(本HP) |
しかし、私たちの研究プロジェクトの定義は、先行研究の定義と大きく異なる特徴があります。それは、単に集団・社会と良い関係性を持つだけでなく、個人として自律していることと、集団として調和していることを併せ持つ状態であることを強調している点です。
これは、私たちが東アジアの全体論的自己の思想であるSelf-as-We自己観 (参考文献9)を意識して、Social Well-beingを捉えていることと関係しています。
Social Well-beingの指標
また、Social Well-beingを測定・運用する試みも進んでいます。表2に、Social Well-beingに関連する指標をいくつか載せています。私が調べた範囲では、定義と同様に、標準的な指標も存在しておらず、様々な指標が提案されています。
例えば、Larsonによれば、Social Well-beingは、社会的適応(social adjustment)と社会的支援(social support)という2つの概念で構成されるとされています (参考文献10)。
一方、Keyesによれば、Social Well-beingは、社会的貢献(social contribution)、社会的統合(social integration)、社会的実現(social actualization)、社会的受容(social acceptance)、社会的一貫性(social coherence)の5つの概念で構成されるとされています (参考文献11)。
また、先行研究では、Social Well-beingを個人のWell-beingを構成する概念の1つとして捉える見方と、個人のWell-beingに影響を及ぼす外的な要因として捉える見方に分かれているという主張も見られます (参考文献12)。
| 指標名 | 構成概念・領域 | 参照 |
|---|---|---|
| Social Adjustment Scale Self-Report (SAS-SR) | Work, Social and leisure, Extended family, Marital, Parental, Family unit | Weissmanら (参考文献13) |
| Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) | Tangible support, Belonging support, Self-Esteem support, Appraisal support | Cohenら (参考文献14) |
| WHO Quality of Life (WHOQOL) | Personal relations, Sexual activity, Social support | World Health Organization (参考文献15) |
| Social Well-being Scale (SWBS) | Social integration, Social contribution, Social coherence, Social actualization, Social acceptance | Keyes (参考文献10) |
| European Social Survey (ESS) Well-being Module | Inter-personal feeling (Belonging, Social support, Social recognition, Societal progress), Inter-personal functioning (Social engagement, Caring, Altruism) | Huppertら (参考文献16) |
| Neighbourhood Thriving Scale (NTS) | Collective positive effort, Participation, Celebration, Social network pathway, Optimism about the community, Social cohesion, Engagement pathway, Safety, Autonomous citizenship, Positive regard, Low resilience | Baldwinら (参考文献8) |
表2にあるような指標を用いることで、Social Well-beingを測定することができるようになりますが、これで十分かと言えば、そうとは限りません。
図1は、Sungらの研究 (参考文献17)に基づき、概念と指標の関係の枠組みを示したものです。
ピラミッドの最上部にあるSocial Well-beingは、その下部にある主要領域(例えば、職場、地域社会など)から影響を受けます。そしてこれらの主要領域は副次領域(例えば、部署、ボランティアグループなど)で構成され、人々はその副次領域でのイベントや経験から影響を受けます。そしてこのピラミッドの最下部が主観的・客観的な指標であり、主要・副次領域に応じて測定する項目を変える必要があります。この主要・副次領域での充足度が高いほど、総合的にSocial Well-beingが高い状態であると言えるでしょう。

以上のように、指標について見てきましたが、Social Well-beingが多義的であることもあり、結論はまだ出ていない印象です。指標に関しては、私たちの研究プロジェクトにおいても、目的や対象領域に応じてどのような主観的・客観的な指標を用いるべきかについて議論を進めている段階です。また、Social Well-beingがそもそも測定可能な概念であるかについても議論するべきかもしれません。
今後の展望
ここまで、私たちがSocial Well-beingを重視する背景、その定義や指標について触れてきました。
定義を読んでも、正直よくわからないと思われる方もいると思いますし、標準的な指標が存在しないことを踏まえると、Social Well-beingをどのように実現していけばよいかわからないと感じる方もいると思います。
私は、それはこの概念を扱う上でやむを得ないことだと思いますし、統一的な定義や標準的な指標に注力することに大きな意味はないのではないかと感じています。むしろ、研究者・実践者が、対象とする人々や目的に応じて、Social Well-beingを定義づけ、指標を新たに開発したり、既存の指標を選択したりする必要性があると考えています。
私たちの研究プロジェクトでは、定義に示したような、個人の自律と集団の調和が両立された状態をどのように定量化するかについて議論を進めています。
また、定量化と並行して、インタビュー調査やエスノグラフィー調査といった質的な調査手法を組み合わせることで、現象を多角的に理解することも重視しています。
そして今後は、それらの知見を、Social Well-beingのための情報通信技術のデザインに活用していく予定です。最終的には、これらの取り組みを通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。
参考
- 国土交通省:令和4年度テレワーク人口実態調査:
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001598357.pdf(参照日 2024年1月25日) - 日本電信電話株式会社:リモートワークを基本とする新たな働き方の導入について:
https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/06/24/220624a.html(参照日 2024年1月25日) -
Allen, T. D., Golden, T. D. and Shockley, K. M.:
How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings, Psychological Science in the Public Interest, Vol. 16, No. 2, pp. 40–68 (2015). - World Health Organization: Constitution of the world health organization: https://www.who.int/about/governance/constitution(参照日 2024年1月25日)
-
Russel, R.: Social health:
An attempt to clarify this dimension of wellbeing (1973). -
Keyes, C. L. M. and Shapiro, A. D.: Social Well-Being in the United States:
A Descriptive Epidemiology., The John D. and Catherine T. MacArthur foundation series on mental health and development. Studies on successful midlife development., pp. 350–372, The University of Chicago Press (2004). -
Linton, M.-J., Dieppe, P. and Medina-Lara, A.:Review of 99 self-report measures for assessing well-being in adults:
exploring dimensions of well-being and developments over time, BMJ Open, Vol. 6, No. 7, p. e010641 (2016). -
Baldwin, C., Vincent, P., Anderson, J. and Rawstorne, P.: Measuring Well-Being:
Trial of the Neighbourhood Thriving Scale for Social Well-Being Among Pro-Social Individuals, Int J Community Wellbeing, Vol. 3, No. 3, pp. 361–390 (2020). -
渡邊淳司,村田藍子,高山千尋,中谷桃子,出口康夫:
「われわれとしての自己」を評価する–Self-as-We尺度の開発–,京都大学文学部哲学研究室紀要, Vol. 20, pp. 1–14 (2020). -
Larson, J. S.:
The measurement of social well-being, Social Indicators Research, Vol. 28, No. 3, pp. 285–296 (1993). -
Keyes, C. L. M.:
Social Well-Being, Social Psychology Quarterly, Vol. 61, No. 2, pp. 121–140 (1998). -
Cicognani, E.:
Social Well-Being, Encyclopedia of Quality of Life and Well-being Research, pp. 6193–6197, Springer, Dordrecht (2014). -
Weissman, M. M. and Bothwell, S.:
Assessment of Social Adjustment by Patient Self-Report, Archives of General Psychiatry, Vol. 33, No. 9, pp. 1111–1115 (1976). -
Cohen, S. and Hoberman, H. M.:
Positive Events and Social Supports as Buffers of Life Change Stress1, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 13, No. 2, pp. 99–125 (1983). -
World Health Organization:
Programme on mental health: WHOQOL user manual (1998). -
Huppert, F. A., Marks, N., Clark, A., Siegrist, J., Stutzer, A., Vittersø, J. and Wahrendorf, M.: Measuring well-being across Europe:
Description of the ESS Well-being Module and preliminary findings., Social Indicators Research, Vol. 91, No. 3, pp. 301–315 (2009). -
Sung, H. and Phillips, R.:
Conceptualizing a Community Well-Being and Theory Construct, Social Factors and Community Well-being, pp. 1–12, Springer, Cham (2016).
著者