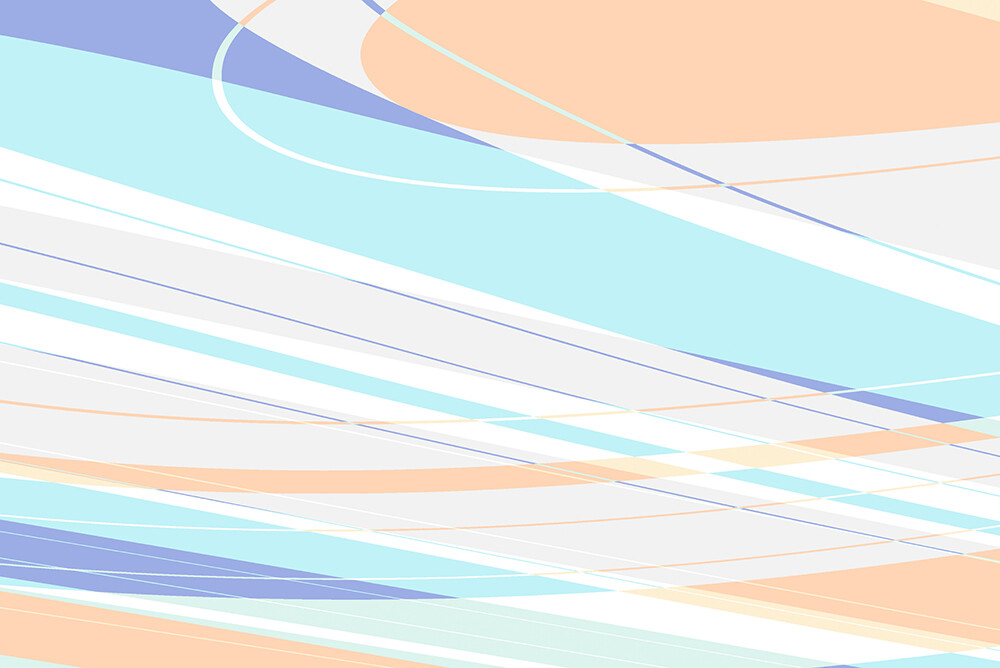
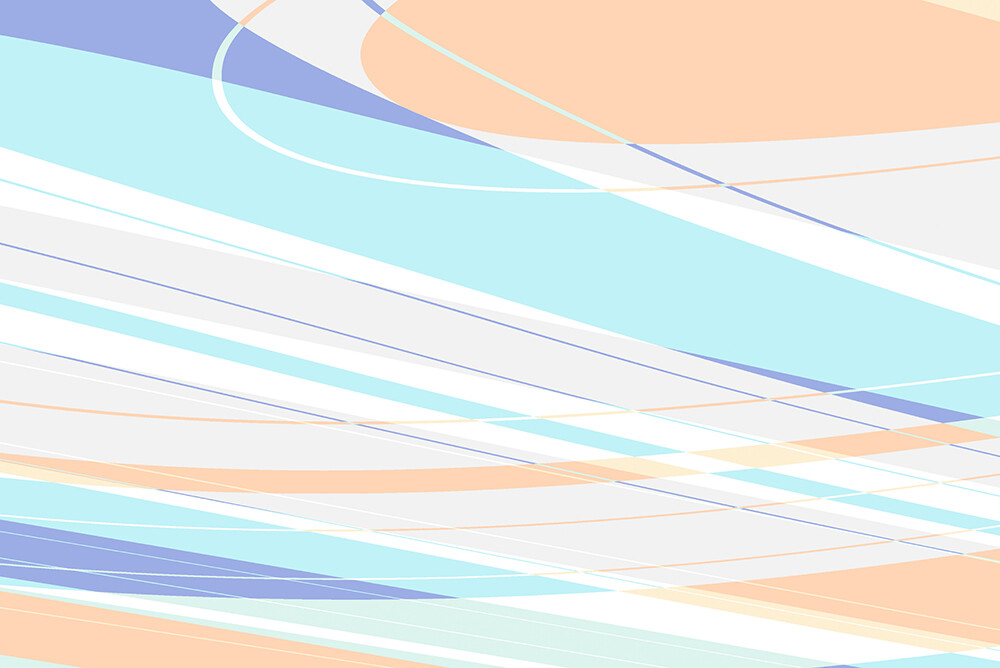
社会システム変容の研究と有識者のコラム集 コラム④ ICT
ウェルビーイング時代の生産性
慶應義塾大学 総合政策学部
教授
國領 二郎
ウェルビーイングが重視される時代にどのような開発目標を定めるべきか再考をしないといけない時代が来ていると思う。本稿では特に投入したインプットに対してアウトプットの大きさを経済的に測る「生産性」をどのように見直せばいいか考えてみたい。イノベーション政策なども基本的に新しい技術を開発することで効率性を高めたり、新しい利便性を生み出したりして、企業の利益成長や新しい産業を創出することに力点が置かれてきた。成果の評価もITが全要素生産性をどれくらい高めたか、といった考え方で語られる場合が多い。日本の経済成長を支えてきた重要な考え方であってきたことを認めつつ、今、それらをウェルビーイングの視点で見直すべき時が来ていると思う。
生産性概念を否定したいわけではない。ウェルビーイングの世界でも、情報技術が生産性を高めることへの期待は引き続き大きい。介護労働者などの人手不足を解消したり、待遇改善をはかったりする上で当然のように課題となるのが、そのような作業の労働生産性の低さだ。介護作業には要介護者の個別の体形や要望に基づくきめ細かい作業が必要で、典型的な労働集約的な産業だった。一方で高齢者や福祉行政の負担能力は限られており、結果として重労働で精神的に負担が大きい仕事に対して高報酬を差し上げられない状況が続いている。このような仕事に対してロボットや遠隔見守りシステムを活用することによって、労働生産性を高め、待遇を改善しようというのはごく自然な発想といっていいだろう。一人で対応できる要介護者の数を増やしたり、労働に伴う負担を減らしたり、それらによって浮いた時間を人間的な会話を増やすことに使ったりすることで、報酬も職務満足も高まり、介護サービスを受ける側にもプラスの効果が期待できる。
しかし、かといって労働生産性を技術開発の目的にしたり、最終的な成功の指標としてしまったりすると大きく間違えるのではないか。そんな問題意識を持つ開発者の方々が増えてきていると感じている。介護労働の例で高齢者のおむつ替えのロボット開発を想定して考えてみよう。ロボットが介護労働者を支援しておむつ交換を効率的に行うシステムと、高齢者が自分で取り換えることを支援する仕組みがあって、仮に前者の方が「生産性」的には効率的だったとしても、効率的におむつを換えられる高齢者はモノ扱いをされ、自律性を奪われることに抵抗感を感じるだろう。たとえ労働生産性が相対的に低くなっても後者が実現するならば、そちらの開発に大きな資源を投入すべきと考えたいところだ。
このような違和感が生まれるようになってきたことにはいくつかの理由があると思われる。新しい指標を考える上で、現在の問題を理解することが重要なので、分析してみよう。
第一に挙げられるのは、ワイヤレス技術の発達などによって、情報技術が従来よりもはるかに人間に近いところにまで到達していることだ。より人間の深いところで影響し始めている。昔ならば、技術の利便性は商品やサービスの購入という形で経済行為を介して間接的に人間に影響していた。それが今はITが人間の生活や場面に大きく関与するようになってきている。AIなどが心の奥の感情や感性に直接入り込む時すらある。それらへの貢献(や負担)は必ずしもお金では計測できない。ITの価値が単に経済的な取引の大きさではとらえられなくなっているのだ。
そのような価値の大きなものとして、社会的包摂があげられる。これがITを活用したウェルビーイングを実現する上での中心テーマともいえる。先の介護の例をとってみても、システムが目指したい最大の目標は高齢者や障がい者が自立し、社会的な活動に参加できる状態を作ることだと言っていい。全ての人間が自己肯定感を持ち、社会活動に参加できると感じられることが幸福につながっていくからだ。ITがそれにどれだけ役立つかをきちんと評価したい。
社会包摂などを考えていると、第二のポイントとして、分子とも分母とも言えない要因が生まれつつあるという認識に至る。人間として社会的価値の創造活動に参加するということは、労力を投入するという意味ではインプットなのであるが、社会参加が出来ていることへの満足感を得られているという意味ではアウトプットとも言える。分子がアウトプットで分母がインプットという構造そのものが揺らいでいる。実はこの現象はマーケティング科学においてはエンゲージされた顧客が労力を投入して商品の価値を高める現象として従来から認識されていた。エンターテイメントなどにおいてファンクラブが果たしている役割などはその象徴的現象といえよう。これが現代的な意味を持つのはITが単に消費者に便益を届ける道具になっているだけでなく、使う現場において、企業と消費者、そして消費者間で価値創造が行われる「価値共創」の場を提供する道具となっているからだと考えることができる。そのような価値共創を活性化できたか否かがIT開発の成功のメトリックということになる。
第三にネット上の無償サービスなど、市場取引によらない形で提供されている価値の存在が大きくなっていることがあげられる。ネット上にはさまざまな形で無償サービスが提供されており、利用されている方も多いだろう。厳密には広告収入や物品販売の形で収益を生み出しているが、ITサービス限界費用(追加一単位サービスを提供する費用)の低さもあって、負担感なく大きな利便性を享受している。その部分については市場取引で価格がついていないため、通常の生産性の計算においてはアウトプットと計算されない。支払っても良い金額と、実際に支払う金額の差は消費者余剰と呼ばれるが、ネット上の無償サービスは大きな消費者余剰を生んでいると考えられており、それはアウトプットとして計算されていない。
以上のような生産性指標の今日的課題の多くはGDP(国内総生産)などのマクロ指標の問題ともいえるだろう。GDPも財やサービスが市場で取引された金額で計算されており、社会包摂の価値、価値共創の価値、無償サービスの消費者余剰も入っていないからだ。国レベルの技術開発政策が、技術によって新しい産業を生み出し、その生み出す市場規模を「経済効果xx兆円」といった表現でアピールすることがあるが、生み出す市場規模だけで考えると開発の方向性を間違えて、社会的な疎外を創り出す技術を生み出しかねない。
社会包摂や価値共創などがウェルビーイングの中心的テーマであることを考えた時に、技術開発の目標や成果評価にもぜひそのような考え方を取り込んでいきたいところである。問題はそれをどのように行うかだ。
非常にわかりやすい生産性のインプット-アウトプットのフレームワークを維持しながら、インプットやアウトプットの中身の見直しをしていくというのは一つのアプローチであろう。というよりも、今のところそれを超えるフレームワークが見当たらないというのが正直なところではないか。特にアウトプットに社会包摂や価値共創で生み出される価値を入れ込んでいくことが当面の焦点になるだろう。残念ながら社会包摂や価値共創から得られる満足感などは、かなり主観的なもので、絶対的な水準として計測するのは難しいのだろうと思われる。そのような制約を認識した上で、客観的な社会包摂の達成度、価値共創の水準変化の計測などは可能ではないか? そして、事前に設定した目標の達成度を計測することも可能だろう。技術間の比較評価などをしたいので、横比較が可能となる指標づくりや調査方法などについての研究も行っていきたいところである。
少し先を見た時にもっと直接的に脳の活動を計測することで、ウェルビーイングの達成度を測るということもあり得るのかもしれない。幸せな時に分泌される物質や脳波などで、技術開発によってウェルビーイングがどれほど高まったかの評価をする日が来ることも想定してもいいかもしれない。そのような計測の仕方に危険を感じる人がいるかもしれないので、社会的コンセンサスを得ながら進めていくのだろう。
いずれにしてもウェルビーイングを開発指標に取り込むというのは人間の幸福とは何かという深淵な問題に答える作業を伴う。その問いの深さを十分に認識しながら、よりましな開発目標をたてていきたいものである。
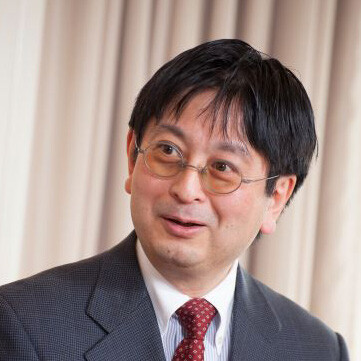
國領 二郎
1982年東京大学経済学部卒。日本電信電話公社入社。1992年ハーバード・ビジネス・スクール経営学博士。1993年慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授。2000年同教授。2003年同大学環境情報学部教授、2006年同大学総合政策学部教授(現在に至る)などを経て、2009年より2013年総合政策学部長。また、2005年から2009年までSFC研究所長、2013年より2021年5月慶應義塾常任理事を務める。