2025/05/14
酸素原子のわずかな「ズレ」で磁石を反転
~強磁性ワイル酸化物「単層」における高効率磁化反転で低消費電力磁気メモリへ道を拓く~
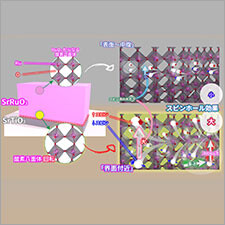
東京大学大学院工学系研究科の堀内皓斗大学院生(博士課程1年)、金田(高田)真吾大学院生(博士課程3年:研究当時)、田中雅明教授、大矢忍教授らのグループと、日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田明、以下、NTT)は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の荒木康史研究副主幹、家田純一グループリーダー、北海道大学大学院情報科学研究科の山ノ内路彦准教授、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構の佐藤幸生教授らと共同で、SrRuO3(以下、SRO)というワイル半金属*1と呼ばれる特殊な磁石の薄膜に電流を流すだけで、その磁化(N極とS極)の向きを反転させることに成功しました。電流から、磁化に作用する回転力「スピン軌道トルク(SOT)」*2,を得るために、今までは、磁石の薄膜と高価な重金属薄膜を接合させた二重層が用いられてきました。しかし、作製に高いコストがかかることに加え、磁化を反転させるために107 Acm-2程度の大きな電流密度(断面の幅を数10 nmと仮定した場合、10μA(10-6 A)以下の電流に相当)を要することが問題でした。研究グループは、SRO薄膜内に10 pm(10-11 m)程度の極微小なRuO6格子の回転が起こっている領域があることを突き止め、それにより劇的にスピンホール効果*3が増大し、磁石「単層」であっても大きなSOTが得られることを明らかにしました。その結果、本研究では、従来の10分の1程度の3.1×106 Acm-2の電流密度での磁化反転が実現されました。本成果は、単結晶中の原子のわずかな「ズレ」を積極的に利用し、SOTを用いて磁化を低い消費電力で制御するための新たな材料設計の指針を与えるものです。今後、人工汎用知能(AI)やニューロモルフィックコンピューティング*4、自動運転システムを支える磁気メモリや磁気センサといった、次世代スピントロニクスデバイス*5の基盤技術になることが期待されます。
発表のポイント
- ワイル半金属と呼ばれる特殊な単結晶酸化物の薄膜でできた磁石「SrRuO3 (SRO)」において、「磁石単層に直接電流を流すだけでN極とS極(磁化の向き)が反転する」という特異な現象を観測しました。
- 薄膜内の酸素原子のわずかな「ズレ」により、電流を流すと磁石内部に大きなスピン軌道トルク(SOT)という力が働くことがわかりました。これにより、高品質のSRO単層膜で世界初の磁化反転を従来技術のわずか10分の1の電流密度3.1×106 Acm-2(断面の幅を数10 nmと仮定した場合、10μA(10-6 A)以下の電流に相当)で実現しました。
- 本研究成果は、磁石の向きを低い消費電力で簡単に制御するための新しい材料開発のヒントとなるものです。次世代のスピン軌道トルク磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(SOT-MRAM)をはじめとした新たな省エネルギーデバイスの実現につながるものと期待されます。
実験結果から想定されるデバイスの動作原理
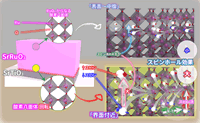 実験で用いたSrRuO3/SrTiO3からなる高品質単結晶ヘテロ構造では、SrRuO3とSrTiO3との界面(左図、白破線)近傍で、両者の材料の違いによりRuO6からなる酸素八面体がわずか10 pm(10-11 m)程度回転していることが明らかになった。この領域では、電流が非常に高効率でスピン流に変換される。このスピン流によって生じるスピン軌道トルクの働きによってSrRuO3の磁化が反転することが明らかになった。
実験で用いたSrRuO3/SrTiO3からなる高品質単結晶ヘテロ構造では、SrRuO3とSrTiO3との界面(左図、白破線)近傍で、両者の材料の違いによりRuO6からなる酸素八面体がわずか10 pm(10-11 m)程度回転していることが明らかになった。この領域では、電流が非常に高効率でスピン流に変換される。このスピン流によって生じるスピン軌道トルクの働きによってSrRuO3の磁化が反転することが明らかになった。
研究の背景
磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)*6は磁石の磁化(N極とS極)の向きを0と1に対応させることでデータを記憶するメモリデバイスです。電源を切ってもデータが消えないため動作に要する消費電力が小さく、既存の半導体メモリデバイスに代わる次世代デバイスとして期待されています。最近の研究により、MRAMを構成する磁石の磁化の向きを、電流で高速に反転できることが明らかになっています。また高集積化が可能で、AI、ニューロモルフィックコンピューティング、自動運転車のシステムなどにも利用できるものと期待されています。磁化を反転させるためには、電流の正体である電子の電荷の流れを、磁石の最小単位である電子のスピンの流れ(スピン流)*7に変換する必要があります。この変換機構を介して磁化に作用する回転力がスピン軌道トルク(SOT)です。
SOTによる磁化反転には通常、電流からスピン流への変換効率の大きな重金属(しばしばPtなどの高価な貴金属)の薄膜と強磁性*8薄膜を接合した二重層が用いられています。しかし、磁石以外に別の貴金属材料を新たに成膜しなければならない作製コストに加えて、スピン流が強磁性層に注入される際にこうした異種物質同士の界面でスピンが散乱されてしまうなどの理由で、磁化反転には107 Acm-2という大きな電流密度が必要であることが問題となっていました。このように、異種物質界面の存在が、SOT磁化反転の低消費電力化を妨げる要因の一つとされてきました。
そこで、成膜工程を減らすことができ、かつ異種物質界面を必要としない方法として、磁石でありながらSOTも生み出せる「一人二役をこなす物質」の「単層」薄膜を用いた磁化反転の研究が始まっています。強磁性体内部でSOTを生み出すためには、薄膜内の元素分布を不均一にするなどの工夫が必要です。しかし、このような物質では、スピン散乱を最小限に抑えつつ高品質の単結晶薄膜を作ることが難しく、その両立が課題となっていました。このような問題を解決するために、物質が本来もつ特性を最大限に生かせる新しい材料の開拓が求められていました。
研究内容
今回、研究グループは、ワイル半金属と呼ばれる単結晶の酸化物SrRuO3(SRO)の薄膜を、SrTiO3(STO)の絶縁体基板上に成膜し、図1(a)のような十字型のデバイスを作製しました。SROのワイル半金属状態は、2020年にNTTが世界で初めて実証したものです(関連情報[1])。図1(b)に示すように、流す電流を変化させ、その直交方向の抵抗([ホール抵抗] = [ホール電圧]/[電流])を測定しました。ホール抵抗は磁化の大きさに比例します。電流を変化させると、ホール抵抗の値は原点を中心としたループを描きました[図1(c)]。これにより、磁石であるSRO単層に電流を流すだけで、磁化反転が起こることが明らかになりました。反転に必要な電流密度は温度120 Kにおいて3.1×106 Acm-2であり[図1(d)]、一般的な二重層構造におけるSOT磁化反転に必要な電流密度の10分の1程度の小さな値が得られました。なお、本実験では、東京大学とNTTが共同で素子構造や薄膜構造の設計を行い、SRO薄膜の作製はNTTが行い、素子加工及び測定は東京大学が行いました。
本研究では、SRO薄膜中のスピン散乱を抑えるために、機械学習を取り入れたNTTの独自技術を用いて成膜条件を最適化し、結晶の乱れが極めて少ない世界最高品質の単結晶薄膜を作製しました。しかし従来の研究では、このような均一な強磁性体単層薄膜において、磁化反転に十分なSOTを得るのは非常に難しいと考えられてきました。そこで本研究グループは、磁化反転の原因を明らかにするために、環状明視野走査透過電子顕微鏡*9を用いて、薄膜広域の構造を詳細に調べました[図1(e)]。一般的に、電流とスピン流の相互変換を効率よく行うには、スピン軌道相互作用が大きい原子番号の大きな「重い」元素が適していると考えられています。しかし本研究では、酸化物を構成する「酸素(O)」のような「軽い」原子にも注目して詳細に調べました。その結果、SRO薄膜内では、SrやRu原子が全体的に秩序正しく並んでいる一方で、酸素原子の位置にだけ「ズレ」がみられ、それがSRO/STO界面付近で特に大きいことがわかりました。このズレは、SROに固有の酸素八面体回転*10に由来するものです。
理論計算の結果、酸素原子のズレはわずか10 pm(10-11 m)程度と小さいものの、このわずかな酸素八面体回転によって、SRO内部で発生するスピンホール効果が5倍以上に増幅されることがわかりました。さらに、この結果を実験結果と比較することで、SRO/STO界面付近の酸素八面体回転に起因して、その周囲の限られた領域からスピン流が生じ、磁化反転に必要な強さのSOTが生み出されている可能性が高いことが明らかになりました。
今後の展望
本研究は、単結晶中の軽元素の微小な「ズレ」が顕著なSOTの増大を引き起こすことを利用して、低消費電力で磁化を制御する新しい方向性を開拓しました。本成果は、SOTを書き込みに利用した磁気メモリであるスピン軌道トルク磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(SOT-MRAM)や磁気センサなど、高機能のデバイスの実用化に向けた材料設計の指針となるものです。研究グループは、NTTが2020年に実証したSROの特殊な強磁性のワイル半金属状態を利用した新コンセプトのメモリの読み出しの実現もめざしています。今後、磁性ワイル半金属を用いた高速低消費電力動作が可能なSOT-MRAMを実現することで、半導体メモリデバイスの置き換えや、AI、ニューロモルフィックコンピューティング、自動運転システムといった分野の発展に寄与することが期待されます。
関連情報
[1]ニュースリリース:「世界で初めてエキゾチックな準粒子の量子的電気伝導を観測」(NTT物性科学基礎研究所、2020年10月9日)
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/10/latest_topics_202010092023.html
論文情報
掲載誌: Advanced Materials
論文タイトル: "Single-Layer Spin-Orbit-Torque Magnetization Switching due to Spin Berry Curvature Generated by Minute Spontaneous Atomic Displacement in a Weyl Oxide""
著者: Hiroto Horiuchi*, Yasufumi Araki*, Yuki K. Wakabayashi*, Jun'ichi Ieda, Michihiko Yamanouchi, Yukio Sato, Shingo Kaneta-Takada, Yoshitaka Taniyasu, Hideki Yamamoto, Yoshiharu Krockenberger, Masaaki Tanaka*, and Shinobu Ohya*
用語解説
- *1 ... ワイル半金属
- 電子があたかも質量ゼロの粒子として振る舞う特殊な3次元の金属物質。反対の性質をもつ2種類の電子がペアとして存在している。電気と磁気が絡む新奇現象や非散逸な伝導特性をもつことから、次世代機能性デバイスへの応用が期待されている。SrRuO3のワイル半金属状態は2020年にNTTが世界で初めて実証した。
- *2 ... スピン軌道トルク(SOT)
- 電流を流した際に、それと垂直方向に生じるスピン流(注7)が、磁石の磁化(N極とS極)に与える回転力。SOTを用いることで、低消費電力で高速に磁化を操作することができるため、次世代の高機能メモリや論理回路への応用が期待されている。
- *3 ... スピンホール効果
- 電流に対して垂直な方向にスピン流(注7)が生じる現象。強いスピン軌道相互作用をもつ物質中で見られる。
- *4 ... ニューロモルフィックコンピューティング
- 人間の脳の神経細胞(ニューロン)の機能を模倣したコンピューティング手法。
- *5 ... スピントロニクスデバイス
- 「スピン」は、電子がもつスピン角運動量やスピン磁気モーメントの向きの自由度のことで、磁石の磁性の起源となっている。スピントロニクスデバイスは、電子の電荷の自由度に加えてスピン自由度も活用したエレクトロニクスデバイスのこと。高い機能性や低消費電力での動作が期待されている。
- *6 ... 磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)
- 強磁性体*8/薄い絶縁体/強磁性体の3層構造で構成される磁気トンネル接合(MTJ)と呼ばれる素子を用いた記憶素子。強磁性体の磁化の向きによって、MTJの抵抗が変わる性質を情報ビットの「0」「1」に対応させる。電源を切っても記憶が保持できる「不揮発性」と高速動作が両立できるため、次世代省エネルギーデバイスとして期待されている。
- *7 ... スピン流
- スピンを運ぶ電子の流れ。スピンホール効果によって電流から生成されるスピン流においては、上向きスピンと下向きスピンが同じ量だけ互いに逆方向に流れるため、電荷の流れは生じない。
- *8 ... 強磁性(体)
- 外部磁場がなくても、物質中のスピンの向きがある特定の方向に揃っている状態。この状態にある物質を強磁性体(磁石)と呼ぶ。
- *9 ... 環状明視野走査透過電子顕微鏡
- 走査透過電子顕微鏡は、高電圧で加速した電子ビームを試料に集束させ、それを走査しながら、試料を通過した電子やそこで散乱された電子を検出することで、試料の構造を画像として捉える装置のこと。加速された電子は非常に短い波長をもつため、可視光を用いる光学顕微鏡よりも高い分解能で、原子レベルの詳細な観察が可能となる。透過した電子や、ごく小さな角度で散乱された電子を円形の検出器でとらえる観察手法は「環状明視野法」と呼ばれ、この手法を用いた走査透過電子顕微鏡を「環状明視野走査透過電子顕微鏡」という。電子が散乱される角度は、試料を構成する元素の原子番号の二乗に比例して大きくなるため、この方法では軽い元素の原子も明瞭に可視化することができる。
- *10 ... (酸素)八面体回転
- ペロブスカイト型化合物ABX3中に存在するAX6やBX6の八面体構造が回転する現象。Xが酸素原子である酸化物の場合は、金属原子の周りを囲む酸素(O)原子に変位が生じる。