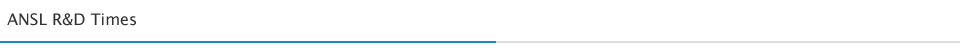
4.実際の設備評価例
地盤変状の定量化及びケーブル被災モデル実験結果より作成したケーブル被災率対照表により,実際の設備データを用い,首都直下型地震を想定した設備評価を実施した例を紹介します.
図5(a)は管路の被災率をMAP表示させた例です。都心部は地下設備を構築した時期が古いことから老朽設備が多く,全体に高い被災率を示しました.また,被災率の高い設備の詳細を見ると1964年以前に建設された印籠継手鋳鉄管の比率が高いことが分かりました.
図5(b)は管路に収容されたケーブルの最大被災率をMAP表示させた例です.このように通信サービスレベルの被災率を評価することで,図5(a)に比べさらなる弱点個所の絞り込みが可能となり,耐震対策が必要な区間の優先順位がより明確となります.
画面のケーブル区間をクリックすることでケーブル個々の詳細情報を閲覧することもできますので,ケーブルの重要度と絡めたさらなる優先順位付けに活用することも可能です.
基盤設備の更改や補修補強を実施するトリガーは,耐震対策の他に設備の老朽化に関する情報,設備の容量不足に関する情報,複数ルートの集約計画,社外工事との共同施工計画,支障移転情報等のさまざまな情報があります.これらを重ね合わせ,将来を見据え,信頼性,経済性,施工性,環境保全性等を考慮した総合評価によりもっとも効果的な対策を実施する必要があります.
図5(b)の赤丸で囲んだ区間は,ケーブルの被災率が10%以上(信頼性評価),1964年以前の鋳鉄管(老朽化評価),ケーブルを増設する空きスペースがない区間(設備容量評価)を重ね合わせた区間を示しており,最重点の弱点個所を表示しています.
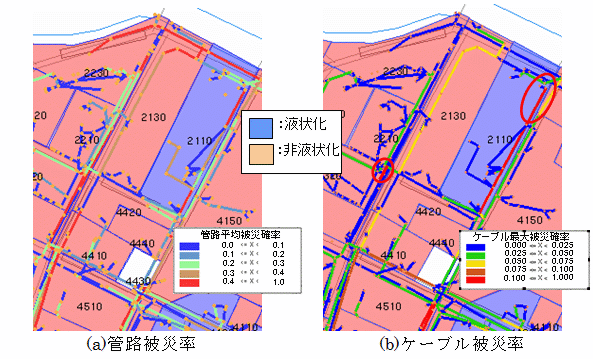
図5(a)は管路の被災率をMAP表示させた例です。都心部は地下設備を構築した時期が古いことから老朽設備が多く,全体に高い被災率を示しました.また,被災率の高い設備の詳細を見ると1964年以前に建設された印籠継手鋳鉄管の比率が高いことが分かりました.
図5(b)は管路に収容されたケーブルの最大被災率をMAP表示させた例です.このように通信サービスレベルの被災率を評価することで,図5(a)に比べさらなる弱点個所の絞り込みが可能となり,耐震対策が必要な区間の優先順位がより明確となります.
画面のケーブル区間をクリックすることでケーブル個々の詳細情報を閲覧することもできますので,ケーブルの重要度と絡めたさらなる優先順位付けに活用することも可能です.
基盤設備の更改や補修補強を実施するトリガーは,耐震対策の他に設備の老朽化に関する情報,設備の容量不足に関する情報,複数ルートの集約計画,社外工事との共同施工計画,支障移転情報等のさまざまな情報があります.これらを重ね合わせ,将来を見据え,信頼性,経済性,施工性,環境保全性等を考慮した総合評価によりもっとも効果的な対策を実施する必要があります.
図5(b)の赤丸で囲んだ区間は,ケーブルの被災率が10%以上(信頼性評価),1964年以前の鋳鉄管(老朽化評価),ケーブルを増設する空きスペースがない区間(設備容量評価)を重ね合わせた区間を示しており,最重点の弱点個所を表示しています.
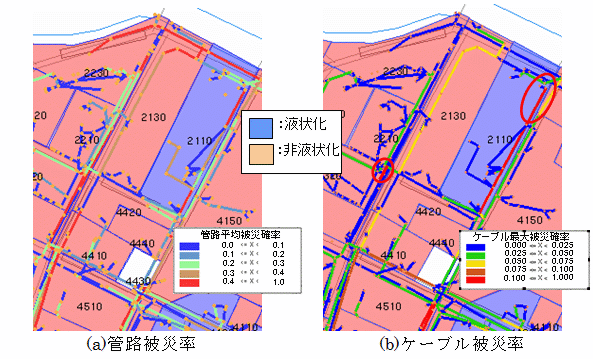
図5 被災シミュレーションMAP表示例
|
3.開発したケーブル被災判定AP |
TOP |
5.その他の機能追加 |
