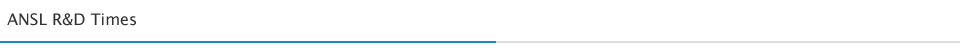
現在、弊所での開発は終了しております
傾斜地における下部支線設計技術を確立!
支線ブロックの傾斜地における地耐力算出式
下部支線(支線ブロック)の地耐力に関する実用理論式を確立しました。ここでは、実用理論式を導き出すために行った実験概要と、実験から明らかになったメカニズムについて説明します。
背景
| 現行の下部支線の適用は、平坦地に対し支線角度25?45°で設置することを標準としています。しかし実施工においては、必ずしも平坦地のみに下部支線を設置できるとは言えず、傾斜地における下部支線の適用明確化(設計方法・設置形態等)が望まれています。 | 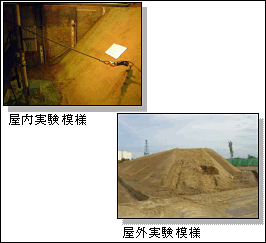 図1 実験模様 |
概要
- ◆現行の設備構築方法とターゲットとする下部支線形態
- 現行の下部支線には支線アンカ、支線ブロック、スパイキボルト3つの設備形態があり、その適用は、標準的には全て平坦地での適用となっています。今回傾斜地における適用を検討するにおいて、3つの設備形態のうち、傾斜地での施工性を考慮し、「支線ブロック」をターゲットとして検討を行いました。
今後の予定
実際に施工される地盤の不均一さを考慮して、採用する土質物性値等の前提条件を確定した後、傾斜地における適用領域を明確にする予定です。
担当者※当記事のお問い合わせは受け付けておりません
光アクセス網プロジェクト アクセスデザイングループ
三浦 重宏(主幹研究員)、小林 康雄(研究主任)、桑畑 秀哉
|
TOP |
1.現行の設備構築方法とターゲットとする下部支線形態 |
