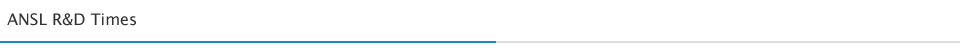
光ファイバの回線利用有無を確認する試験技術
光ファイバの曲げ部から光信号を入出力可能に
曲げを付与した光ファイバに外部から光信号を入出力させることで、光回線の利用有無を確認する試験技術を確立しました。
背景
PON(Passive Optical Network)システムを用いたフレッツ光サービスの回線開通工事では、工事対象の光ファイバを特定するために、フィールド(工事現場)で光回線の正確な情報を確認する必要があります。しかしながらPONシステムにおいては、光スプリッタが伝送路に配置されているため、通信局舎からフィールドの光ファイバに送った試験信号は、光スプリッタによって分岐されたすべての光ファイバに送られてしまいます。そのため、従来の光ファイバ試験測定技術では、分岐された光ファイバすべての情報が重なり混じりあってしまうことから、正確に光回線の情報を確認することが出来ませんでした。そこで、フィールドで光ファイバの回線利用状況を把握するための技術として、光ファイバを曲げることで発生する特性を利用した新たな試験測定技術を確立しました。
概要
光ファイバ中における光信号は、光ファイバのコアと呼ばれる領域内で反射を繰り返しながら伝搬します。しかしながら、光ファイバ中を伝搬している光信号は、光ファイバが曲げられてしまうとコアの領域内で反射できなくなってしまい、光ファイバから漏洩してしまいます。このような光ファイバの性質は伝送路としての観点では望ましくありませんが、光ファイバの試験測定を行うために逆にこの性質を積極的に利用します。フィールドで光ファイバを曲げることにより、その曲げ部からの直接光信号を入力し、さらに光ファイバから戻ってくる光をその曲げ部から漏洩光として出力させることで、光ファイバの設備状況を把握することが出来ます。

図1 光ファイバの曲げ部から光信号を入出力し回線利用状況を確認
今後の予定
今後も光ファイバ設備の施工および試験技術の検討を進め、より効率的かつ柔軟な光通信網の実現を目指した取り組みを実施していきます。
担当者
アクセス運用プロジェクト 施工高度化グループ
井上 研司(グループリーダ)
廣田 栄伸(主任研究員)
飯田 裕之(主任研究員)
納戸 一貴(研究主任)
植松 卓威(研究員)
廣田 栄伸(主任研究員)
飯田 裕之(主任研究員)
納戸 一貴(研究主任)
植松 卓威(研究員)
|
TOP |
